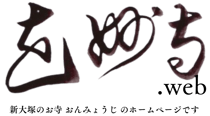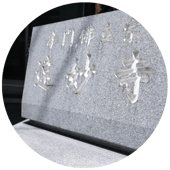- ホ ー ム
- ニュース
- 遠妙寺ご案内
- 本門佛立宗の教え
- 体験談
- 大切な人のお教化
- ケガと肺炎のお罰で気づかされたこと、役中後継者育成のお計らい
- ヴィンセントくんの身体回復(前編)
- ヴィンセントくんの身体回復(後編)
- 幹事長のお役のご奉公をさせていただいて
- 念願の母をお教化成就!
- 入信した母のご利益
- はじめて「お助行」をいただいて
- 入信の動機
- 命をいただいて
- 根気強いご祈願でいただいたご利益
- マニラ別院のご利益談
- コロナ禍でも御宝前に守られて
- 身体回復・無事息災のご利益をいただいて
- コロナ禍で頂いたご利益
- 病気平癒のお計らい
- 本門佛立宗との出会いと心の変化
- 信行体験談バックナンバー
- 試験合格で不思議な体験
- もうダメかと思ったとき
- 就職活動で頂いたご利益
- 御宝前にお任せして就職成就
- 職場の人間関係と心の謗法
- 信心増進で当病平癒
- ガン平癒
- 交通事故でいただいたご利益
- お助行のご利益をいただいて
- 生かされている!心筋梗塞からの生還
- 御供水のありがたさ
- 御供水で手術後の不快感がなくなる
- 御供水で事故の痛みが消える
- 尿管結石、一週間の朝参詣と御供水で・・・
- 御灰さんで不思議なご利益
- 難病と教化親の出会い
- 脳出血から奇跡の回復
- 御宝前から授かった念願の女の子
- 不思議としか思えない妙法の妙
- 無事出産、手術成功の現証ご利益
- 母のご信心と大きなご利益
- 教化したからこそお知らせが
- 御題目口唱のご利益
- 大いなる回り道の末に
- 祖父母の入信とご信心の喜び
- 母の臨終で学んだこと
- ご本意にかなう転居先発見
- 体験談ビデオ
- お墓・納骨のご相談
- ご信者用
- 飯能別院
用語集
か行
教化(きょうけ)
教え導き、正信へ変化させる意で、一般社会に働きかけて一人でも正しい信心に入らしめ苦しみから救おうとする行ない。菩薩行の根本。
教務・講務(きょうむ・こうむ)
僧侶を教務といい,信者,信徒を講務と呼ぶのが佛立宗の習慣。壇家や壇徒という名称は用いない。
弘通(ぐづう)
法がひろく広まること、及び広めること。正法を世間に広め、教え導くことで、日蓮聖人は、全世界弘通を理想とした。
下種結縁(げしゅけちえん)
妙法、御題目を人の心の底に植え付けて(下種)、仏果の縁を結ばせる(結縁)こと。
現証利益(げんしょうりやく)
熱心に信心することによって、願いが叶うこと。妙法の正しさと、未来成仏とが願う余地のない現実の証明として眼の前に現われることをいう。一般でいう“現世利益”とは違う。
御教歌(ごきょうか)
佛立開導日扇聖人が、法華経の高遠深広な教理と修行の方法を、平易な和歌に詠み込んだもの。およそ三千余首が伝えられる。
御宝前(ごほうぜん)
一般的には神仏をまつった場所の前を尊んでいう言葉。佛立宗では御本尊を奉安した御戒壇をいう。
御法門(ごほうもん)
一般にいう説教・法話の意で、本門佛立宗では、お寺やお講で説き示される教えのこと。正しい信心の在り方や仕方を学ぶ基本。もともとは仏の教えのことで、その教えの門から入ってさとりに到るといわれた。
御妙判・御指南(ごみょうはん・ごしなん)
御妙判とは、宗祖・日蓮聖人の御書の一節であり、御指南とは、門祖日蓮聖人・開導日扇聖人、その他先師の御書の一節をいう。御法門のなかで、これらの御書の一節を引用し、その内容に誤りないことを証明する。